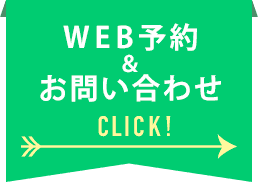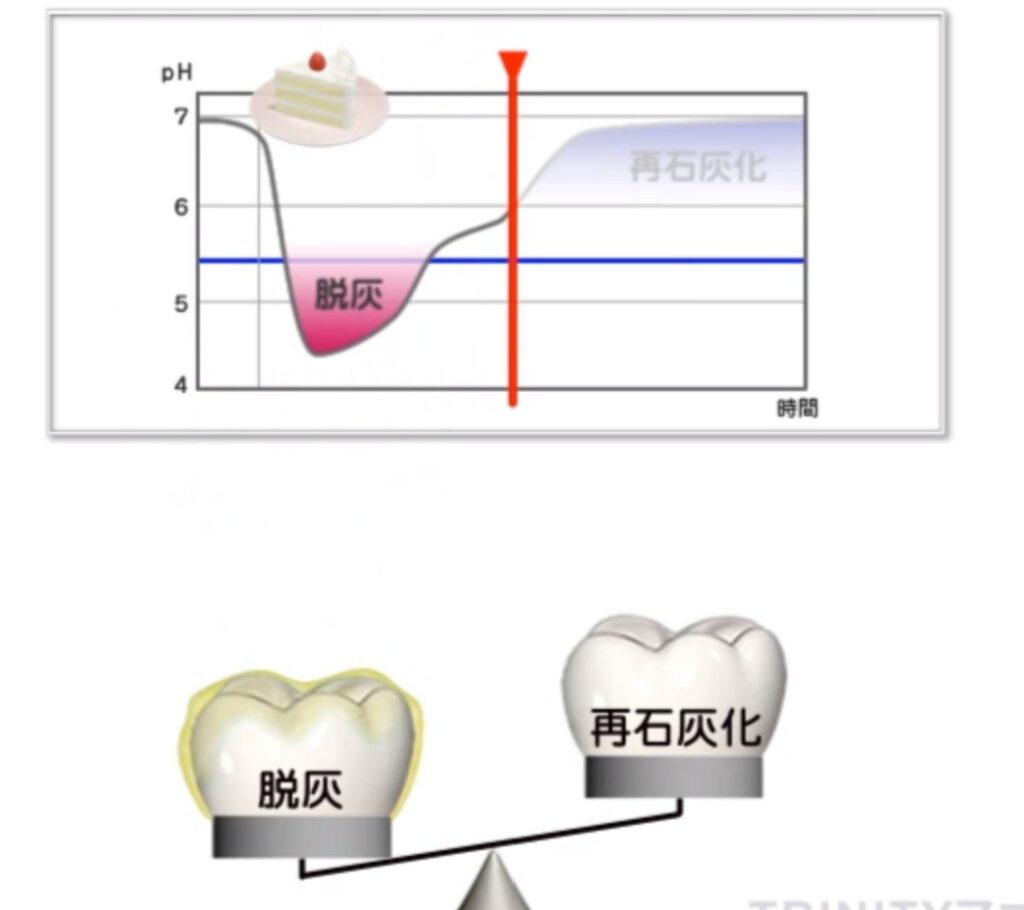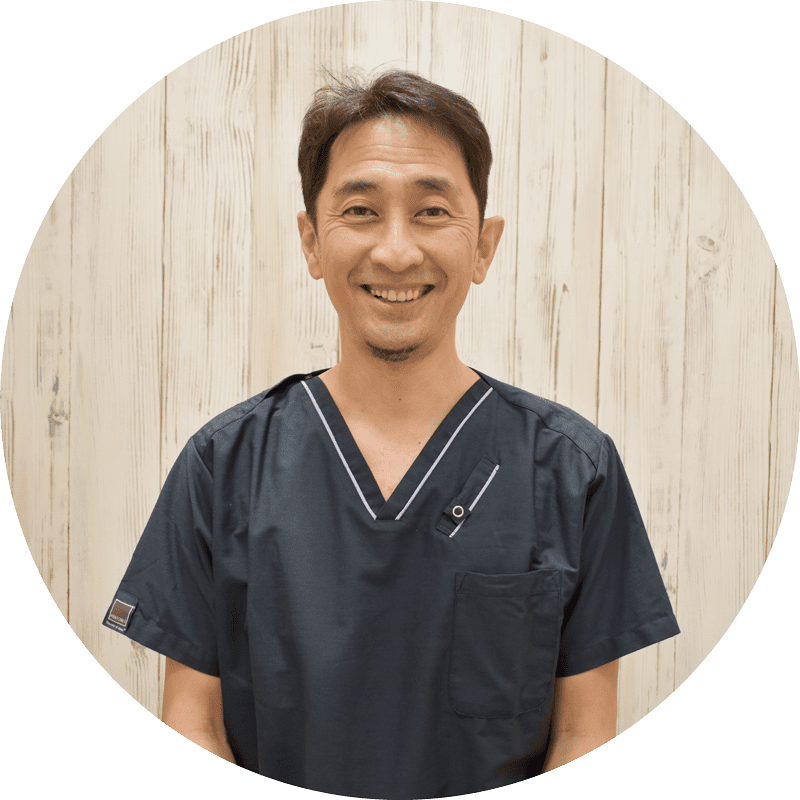こんにちは。
今回のブログは、誰もが一度は経験したことのある「口内炎」について、ちょっと掘り下げてお話ししたいと思います。
口内炎は、口の中にできる小さな白いできもの。
歯があたるたびにチクッと痛くて、食べ物を食べるのも億劫に…。
見た目は地味ですが、日常生活をネガティブにさせてしまう、口内炎の発症する原因と対処法について詳しく説明します。

■ 口内炎ってそもそも何?
口内炎とは、口の中の粘膜にできる炎症のことです。
舌、頬の内側、唇の裏、歯茎など、どこにでもできる可能性があります。
医学的には「アフタ性口内炎」「カタル性口内炎」「ウイルス性口内炎」など、
いくつかのタイプがありますが、一般的によく見られるのは
アフタ性口内炎です。
では、口内炎は一体なぜできるのでしょうか?
■ 原因その①:傷ついた粘膜
一番多いのが、物理的な刺激によって粘膜が傷つき、
その部分が炎症を起こしてしまうパターン。
例えば、食事中にうっかり口の中を噛んでしまったり、
熱すぎる食べ物でやけどをしたり、固い食べ物(ポテチとかフランスパン)で
粘膜がこすれて傷つくと、その部分が炎症になって口内炎になります。
また、歯並びが悪かったり、自分の口に合わない入れ歯や矯正器具が
口の中を慢性的に刺激している場合も口内炎を発症するため、注意が必要です。
■ 原因その②:ストレスと疲れ
口内炎って、仕事が忙しかったり、寝不足が続いた時にできやすい記憶はないでしょうか?
それは、体の免疫力が落ちているサインだったのかもしれません。
ストレスや疲労がたまると、体全体の免疫力が低下し、普段は跳ね返しているようなちょっとした刺激や菌にも負けてしまい、口内炎として現れてしまうのです。

■ 原因その③:栄養不足
特に意識したいのがビタミンB群の不足。
ビタミンB2、B6、B12などは、皮膚や粘膜の健康を保つために重要な栄養素です。これらが不足すると、口の中の粘膜が弱くなり、炎症が起こりやすくなります。また、鉄分や亜鉛の不足も関係するといわれています。
偏った食事やダイエットをしているとき、口内炎ができやすくなるのはこのためです。

※ビタミンB群で押さえておきたい食材は豚肉、鶏肉、さば、かつお。その他、ゴマや玄米、アーモンド、アボカドなどにも豊富に含まれているので、それらをコンスタントに摂取すると良いでしょう。
■ 原因その④:ウイルスや菌の仕業
まれにですが、ウイルスや細菌、真菌(カビの一種)が原因で口内炎になることもあります。
たとえば「ヘルペスウイルス」による口内炎は、水ぶくれのような見た目で、
強い痛みや発熱を伴うこともあります。
「カンジダ菌」という真菌が増えると、白っぽい苔のようなものが口の中に広がる「カンジダ性口内炎」になることも。。。
この場合は自己治療ではなく、医師の診断と治療が必要になります。
■ 口内炎ができたときの対処法
軽い口内炎であれば、だいたい1週間から10日ほどで自然に治ります。でも、痛みが強かったり、早く治したいときは次のような対処法が有効です。
市販の口内炎用軟膏を塗る(ケナログ、アフタッチなど)
うがい薬で口の中を清潔に保つ
刺激の強い食べ物(辛い物、熱い物、酸っぱい物)を避ける
栄養バランスの取れた食事を心がける
ちなみに、口内炎のときにコーヒーやアルコールはできるだけ控えた方がよいでしょう。刺激が強すぎるため、治りが遅くなったり痛みが悪化することも。
■ こんなときは病院へ!
「たかが口内炎」と侮るなかれ。
以下のような場合は、医療機関の受診をおすすめします。
- 2週間以上経っても治らない
- 何度も繰り返す
- 痛みがどんどん強くなる
- 発熱やリンパの腫れを伴う
- 舌や唇の端にしこりのようなものがある
なかには、口腔がんなどの重大な病気が隠れている場合もありますので、
長引く口内炎は必ず相談しましょう。
■ 口内炎にならないためにできること
予防は何よりも大切です。以下のようなポイントを意識してみてください。
- 栄養バランスの良い食事(特にビタミンB群)
- 規則正しい生活と十分な睡眠
- ストレスをためない
- 歯磨きやうがいで口の中を清潔に
- 口の中を傷つけないよう注意
ちょっとした工夫で、口内炎の予防につながります。
まとめ
口内炎は小さな炎症ですが、その痛みはなかなか侮れません。でも、その原因を知って日々の生活で少し気をつけるだけで、予防や早期回復につながります。「最近、口内炎ができやすいな…」と思ったら、体からのSOSのサインかもしれません。
食事や睡眠、ストレスケアを見直して、自分を労わってあげましょう。
それでは、今日もおいしくご飯が食べられる一日になりますように!
医療法人社団天白会有明ガーデン歯科クリニックは、
お口の中の些細なトラブルやお悩み事、検診など、お気軽にご相談できる歯科医院です。また、セカンドピニオンでの受診も受け付けております。
土日祝も20時まで診療しており、駐車場も完備しています。お気軽にご相談ください。
あなたの歯の健康をサポートいたします!
このブログの監修者
医療法人社団天白会
有明ガーデン歯科クリニック
院長 歯学博士 石坂千春
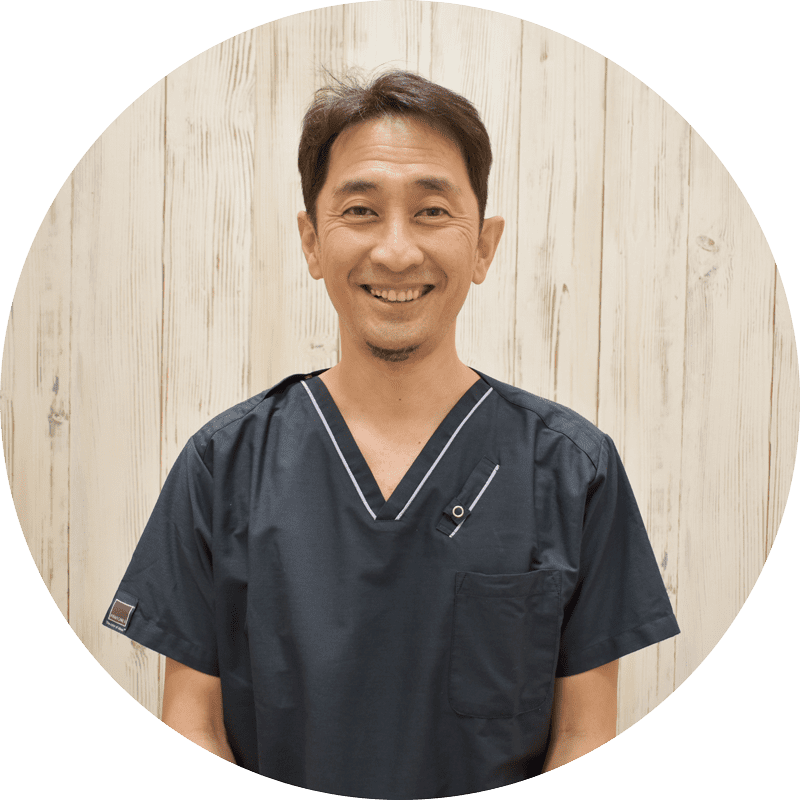
理事長 歯学博士 山田健太郎 日本口腔インプラント学会 専門医